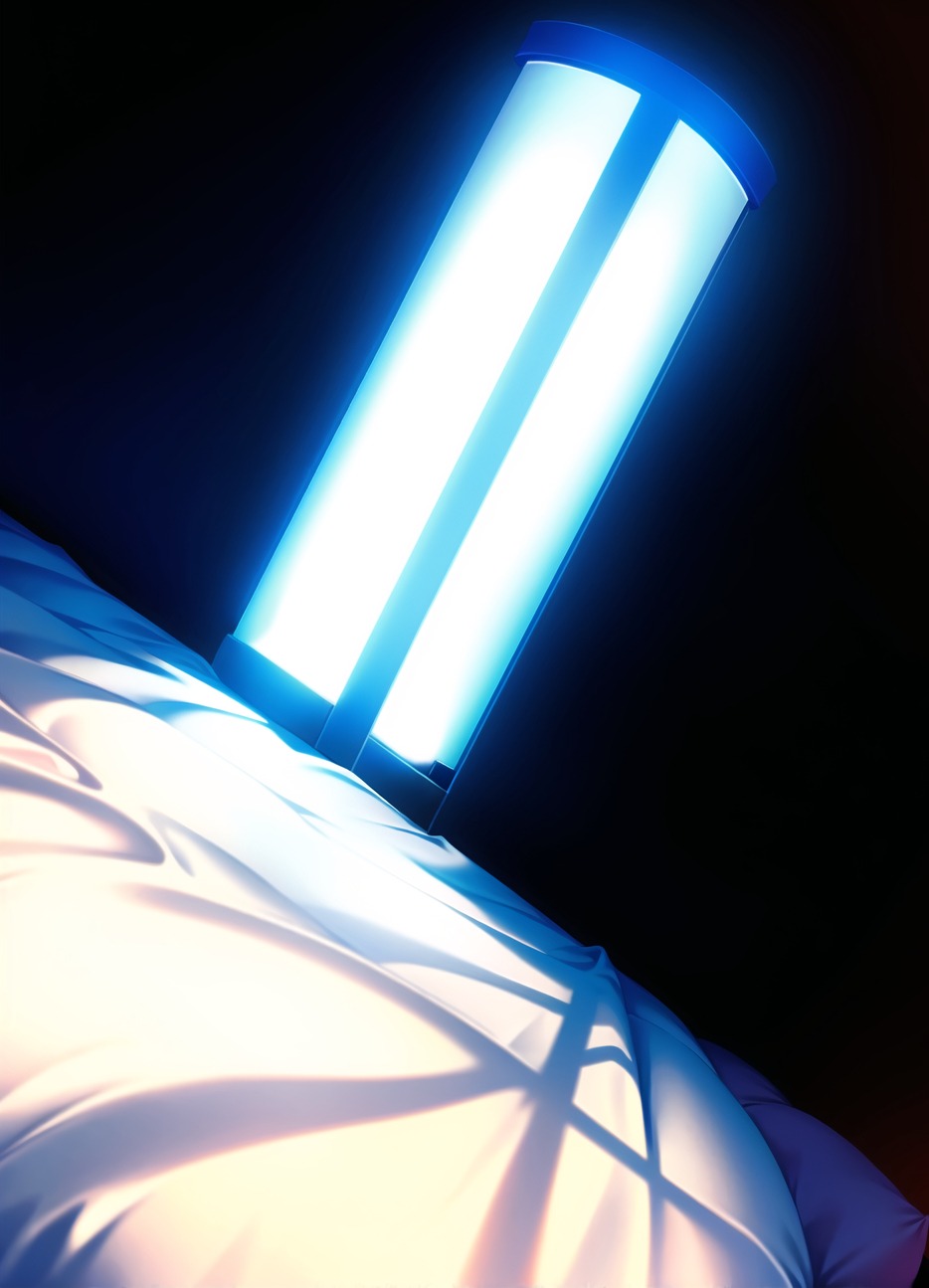「んむっ♥ んはぁ……っぅう…♥♥」
ぴちゃ、ぐちゅ。
儂の咥内で蛇のように細長い舌が暴れ回る。
こちらが後退しようものならすぐにぬるりと絡みつき、逃がさぬよう口内を執拗に犯す。唾液が口許から垂れようともお構いなし。歯列の裏も頬の内側も、ヌルついた舌の感触から逃れることはできなかった。まるで己の欲情を示すかのように、乱暴な舌遣いだ。
「兄貴の奴、久しぶりだからって燃えてやがるな……見てるこっちが恥ずかしくなる程だぜ」
「そうだね。兄ちゃん、そろそろその辺にしとかないと、この元怪獣王とする時間がなくなるよ?」
左右から聞こえるニとサンの声に、今さらのような羞恥を覚える。
しかし、真ん中の首―――今まさに儂と濃厚な接吻を交わしているイチだけは違った。極上の甘味を味わうかのように、夢中でこちらの唇を貪っている。
「ふあぁっ…♥ んむぅっ…ギド、ラぁ…苦しぃ……んぷっ!?♥♥」
息継ぎをする暇すら与えない激しい口付けで呼吸困難に陥りかけ、辛うじて抗議するとようやくこちらの意が通じたらしく、ちゅぱっと音を立てて解放された。
「はぁー…はぁ……こちらの挨拶も、っ終わらぬ内にやってくれるな…! お陰で窒息するところだったぞ」
「ふふっ、そんなに怒るでない。我が愛しい番と久々の逢瀬なのだぞ? 多少なりとも性急になってしまうのは仕方あるまい」
久々―――その言葉に、儂は羞恥と息苦しさから一転し、呆れ果てた。
というのも以前こやつは「監査」と称し、娼館の売店で卑猥な細工入りのボールを目当てに暴れたのを皮切りに、客の見ている前で散々儂を陵辱した。
それだけでは飽き足らず、他の娼婦怪獣たちを嵐のように食い尽くした挙句、ペナルティとしてしばらくの間出禁を食らったのだ。
肉欲の赴くままに好き放題しておいて娼館への謝罪はおろか、こんなふざけたことを抜け抜けと言えるとは―――怒るよりも呆れるほかない。
しかも今回は、誰の介入もなく「夜が明けるまで」という条件付きで儂と交わりたいと言う。そのときには儂の身体はどうなっているか……想像などしたくもなかった。
「……ふん、どの口が言うのだ、恥知らずめ。あの時のお前の蛮行を忘れたか」
「そう怖い顔をしてくれるな。それに今回は純粋に客として来たわけだが、報酬もなしに一晩中交わるのは割に合わぬだろう?そこで、前払いという形になるが…これを飲んでくれないか?」
儂の悪態もどこ吹く風と言わんばかりにギドラは飄々と話を続ける。そのうちにどこからか(怪獣からすれば)小さいボトルを取り出し、机の上へと置いた。
その中にはネック部分の寸前まで詰まった赤黒い液体。遠目からでもコルクの栓を貫き、ほんのりと生臭い匂いが漂ってくる。
「それは何だ? まさか毒物ではないだろうな」
「馬鹿を言うな。これはティアマットの生き血だ」
ティアマットの生き血―――その名を聞いた瞬間に思わず目を見開く。あの好戦的極まりない怪獣の女帝が、自らの生き血をこの偽りの王に易々と捧げただと?それだけギドラのことを気に入っているのか、それとも何らかの取引があったのか。いずれにせよ、ただ事ではない。
訝しむ儂をよそに、ギドラは訊かれてもいないのに淡々と説明を続けた。
「意外、と言いたげだな。顔で判るぞ。奴との交渉には少し時間が掛かったからな」
「交渉とな……一体何を対価にした?」
儂が問いかけるとギドラは肩を揺らし、さも意味ありげな笑みを浮かべる。これは明らかに弟らへ話を振る予兆だ。そしてイチと入れ替わるように、左右の頭部―――ニとサンが口を開く。
「テメェのイキ顔や泣きっ面を事細かに報告しろっていう条件でよぉ、それで納得してくれたんだ」
「ホントに彼奴の強情さには兄ちゃんも辟易したよねぇ。まぁ、そういう訳で交渉が成立した訳さ」
……よりによって儂の淫蕩に満ちた無様な表情を拝みたい、などと心底馬鹿げた条件を掲げられたものだ。しかし、そこまでして儂を辱めたいと考えるあたり、やはりギドラの執着はここを出禁にされた程度では治らないらしい。否、むしろ悪化している気がする。
思案しながら再び件の小瓶に目をやる。ただ赤黒いだけではない。時折薄紅色の煌めきが過っては消えていく、不思議な光景。毒物ではないと説明されたが、それをそのまま飲むのはさすがに抵抗がある。
「その様子だと躊躇しているな? 随分用心深くなったものよ、元怪獣王様。それとも……モスラに逢いたい気持ちが薄らいだのかな?」
「!? 何を戯けたことを……! 儂がこの娼館で男娼をしているのも、全てモスラを救うためだ!」
ギドラの言葉に一瞬、頭に血が上る。だが、なんとか怒りを抑えた。
ここで挑発に乗れば元の木阿弥。それに下手に言い返せば、また奴に揶揄されるのは目に見えている。
「ではやはり飲むしかないな、我が番よ。飲まなければ……分かっているな?」
口調には暗に「臆したか」と嘲る色が混じっている。挙句、鼻で笑われる始末。
しかし、この場で逆上すれば奴の思うツボだ。苛立ちと呆れを隠さぬまま小瓶に視線を戻し、無言でそれを手にしようとした―――その瞬間。
「待て」
イチの一声にぴくりと肩が竦む。
「少し警告しておくが、一気に呷る際には気をつけるが良い。毒味としてラドンに飲ませてみたが、途端に意識を飛ばしてしまってな。丸一日起き上がれなくなってしまった程だ」
「……ッ」
思い切り舌打ちしたかったが、どうにか堪える。致死性の毒ではないのは幸いだが、それでも一体のタイタンが気絶するほどの代物を寄越してくるとは内心呆れる。しかしイチの口調とは裏腹に、その目は「早く飲め」と言わんばかりに爛々と輝いていた。
そんな中、傍らではまたもやニとサンが補足する。
「そんなに疑うなって。兄貴はアンタだからこそと踏んで、奴の生き血を入手してきたんだからよ」
「そうそう。兄ちゃんがこんなに執着している相手なんて滅多にいないからね。ま、僕達が保証するよ、怪獣王サマ」
冠に“元”をつけたり怪獣男娼と一変して、こんな時に都合良く“怪獣王”と呼びおって。
けれども―――今は、文句を垂れている場合ではない。
「……良かろう。だが、儂がこの場で倒れても妙な真似はするなよ。ましてや死姦など言語道断だからな」
「くくっ、流石に我とてそこまでの無粋はせぬ。さぁ、遠慮せずに飲むが良い」
そう促されるまま小瓶を手に取り、中の液体を一息で口の中に流し込む。途端、咥内に血液特有の鉄臭さと生臭さ、そして味覚にどろりと濃厚な苦さが広がる。
「んっ……ぐっ、んくっ……!」
舌触りは決して良いとは言えない。その上喉に絡み付くような粘り気が不快で、反射的に吐き出しそうになるのを我慢すると、強く閉じた瞼に力が入ってしまう。
そう、これはモスラを助けるためだ。奴の下で性奴隷となっていた頃、タイタン達から嫌というほど飲まされてきた精液の味に比べれば幾分かマシだったし、幸いにもたかが少量だ。一刻も早く嚥下を済ませた方が賢明である。
「ほぅ、やはり一滴残さず飲み干すか。ふふ、何と愛い奴よ」
「ラドンもそうやって飲んだっけなぁ。あの時は大変だったぜ」
「彼奴ったら飲み干した途端に頭からポッポー!って音がして、笑える程面白かったよね」
ギドラが思い出話に浸っている傍らで、ようやく全ての生き血を飲み終えた。
喉奥にへばりつく不快感で大きく噎せ返りそうになるが、仇敵の手前何とか堪えてすぐさま嚥下していく。
「ッ……! これで満足か…?」
胃の中がモヤついたかのような不快感を覚え、鼻腔にまで鉄臭さがまとわりつく。このまま奴との遊戯を済ませるよりも先に浴室へ篭って咥内を濯ぎたい気分だが、それすらも眼前の偽りの王は許してくれないだろう。
「その顔を見る限り、相当に酷い味だったらしいな」
「当たり前だ。こんな訳のわからん代物を飲むくらいなら、そこらの雑草でも食っていた方がマシ―――っ!?」
言葉が終わる前に、一際大きな鼓動が鳴ると視界がぐにゃりと歪む。それと同時に全身が心臓になったかの如くドクドクと早く脈打ち、体内にマグマを注ぎ込まれたかのように熱くなる。
「あ……っ!?♥ あ、あっ……!♥」
熱い、腹の奥が焼けるように――否、それ以上に身体中が火照るあまり苦しい。悪酔いしたかのような不快感に思わず膝を突きそうになったが、どうにか持ちこたえた。
「はぁ…はぁ……な、何だ、これは…!? 身体が、熱い……っ!」
「早速効き目が表れてきたようだな。どうだ、気分は?」
問い掛けられてもこちらの脳内はぐわんぐわんと揺さぶられ、まともに思考する事も出来ない。それどころか、下腹部は発情期でもないのに激しく疼いている。
「んぁっ♥ っみ、見るなぁ…♥ あぁッ、見ないでくれぇ……!」
腹筋が戦慄き、股座からそそり立つ逸物の先端からとろとろと透明な滴が零れ落ちる。
それらはいつの間にか、床を汚していた。
まだ「本番」を始める前だというのに、この淫らな有様。これでは怪獣王としての矜持が台無しだ。
己を叱咤したい。だが、もうそんな余裕はない。
「ゴジラ。我の方を見ろ」
「…………っ」
ああ―――今宵の客が。それも、憎たらしい偽りの王が、儂の躰を求めている。
声を出すのも億劫なほどこの忌々しい熱を早く解放してほしい。
一晩中交わり続けて乱れ狂い、この渇望を癒して貰いたい。たとえ、それが反吐が出るほど嫌悪している相手でも。
次々と、そんな欲が湧いてしまう。
「はぁ、はぁっ……ぁ、ぁあっ、んっ……ギドラぁ…っ♥」
「何だ? そちらから我の名を呼ぶとは、珍しいこともあるものだ」
「頼む、からぁ…どうにかしてくれ…っ♥ 気が狂いそうなんだ……♥」
早く、早くこの身を沈めてくれ―――。そう言いたげに上目遣いで偽りの王を仰ぐ。
だが、奴は呆れたように溜息をつくだけで一向に動く気配がない。
宿敵相手に助けを求めるなど、本当は虫酸が走る思いなのに、こうでもしなければこの淫獄からは抜け出せない。身体に溜まった焦燥感は、目の前の雄のモノでなければ決して解消されないのだ。
「成程。我から施される快楽がなければ、達することもできぬ躰になったか……まぁ、気絶しなかったのは良いとして。これから貴殿を好きなだけ抱かせてもらおう」
「はぁ、んぅぅ……っ! じ…焦らすでない、馬鹿者ぉ……っ♥」
「くっく、そう急かすな。夜はまだ長いぞ」
そう言って、ギドラはベッドの上にどさり、と寝転がると、こちらに向かって手招きをした。
その様子はまるで、獲物を呼び寄せる捕食者。一度捕らえられれば、張り巡らされた罠―――もとい金色の肉体に籠絡されるのは必至だろう。
けれど、今の儂にとってその甘美な誘いは決して癒えぬ毒にしかならない。
一歩踏み出すごとに理性が削られていくような感覚。それでも、覚束ない足取りで、奴のもとへと歩み寄る。
「ふふ、見るからに重症だな」
「う、うるさい……!」
「まだ素直になれんようだな……ほら、此方へ来るが良い。貴殿の望むままに、快楽を与えてやる」
ギドラの傍へ寄ると、待ってましたとばかりにニとサンがそれぞれ首を伸ばし、儂の両腕を絡め取る。
息つく間もなくそのまま強引に引き寄せられ、奴の胸元へと顔を押しつけられた。
「―――っ!」
何の抵抗もできぬまま、鼻腔を突くのはギドラの発情したフェロモン。一度鼻腔を掠めれば濃厚な香りが脳髄を焼き、全身に染み渡っていく。
(駄目だ、早く逃げないと……!)
そう思ったはずなのに。それすらも掻き消されるほどにこの芳香は強烈だった。気がつけば、儂は金色の滑らかな体表へと唇を落としていた。
何度も、何度も、求めるように。
「んふっ…♥ んむぅっ……ちゅぱっ、ぢゅぅぅっ……!♥♥」
「おや、随分と熱烈な接吻だな。よっぽど寂しかったらしい」
頭上からクスクスと嘲るような笑い声が降ってくる。
それも当然だ。こんな甘えるかのような激しい口付けなど娼館に勤めて以来、自ら求めたことなど一度もない。
だが、それでも止められない。もっと深く繋がりたい。
ギドラの体温を全身で感じたい。身体がそう訴えていた。
「そんなに我が恋しかったのか? ゴジラ」
「……ッ!」
否定したいのに、言葉が出てこない。これは―――ティアマットの生き血のせいだ。
無理矢理に発情させられているだけ。だから決して、この雄に恋慕など抱いているわけではない。
そう思いたいのに。
「ふふ、図星か。やはり貴殿は淫乱だな。ほら、背鰭が小刻みに輝いているぞ?」
吐息交じりに囁かれた瞬間、ぞくりと背筋が震える。
それは恐怖ではなく、純粋な快楽によるものだ。直接的に鼓膜を震わせるのではない。
脳内に直接響くかのような、ねっとりとした声音。
それが絶えず覆いかぶさるようにして儂の精神や獣慾を否応なく刺激してくる。
「おいゴジラ、甘えるのは良いけど先にやる事あんだろ? ほら、ココとかさ……」
ニの声に促されて視線を向ける。そこには、いつの間にか臨戦態勢となったギドラの二股男根が、天を衝かんばかりにそそり立っていた。
脈打つ先端は、今にも暴発しそうなほど張り詰めている。
その姿を視界に収めた途端―――思わず、喉が鳴った。
「……っ♥」
「どうした? 早々から物欲しげにしおって……先ずはコレに挨拶をするのが、男娼としての礼儀ではないのか?」
普段なら、異形の男根を目の当たりにした時点で息が引き攣るほどの嫌悪感を抱くはずなのに。今は不思議と目が離せない。それどころか、心拍数が異様に高まっていくのを感じる。
頭が、ぼうっとしてくる。
下手をすれば、見つめているだけで達してしまうのではないか?自ずと、口が半開きになる。
「んんっ……♥ はぁ…はぁっ……♥」
「ほら、早くしろ」
忌々しい相手のはずなのに、そちらから急かされるともう限界だ。
我慢できない。
気づけば、儂はそろそろとギドラの胴体から後退していた。
胸筋を掠める男根の熱に打ち震えながら―――遂にはその先端へと舌を伸ばし、ちろちろと舐め始めていた。