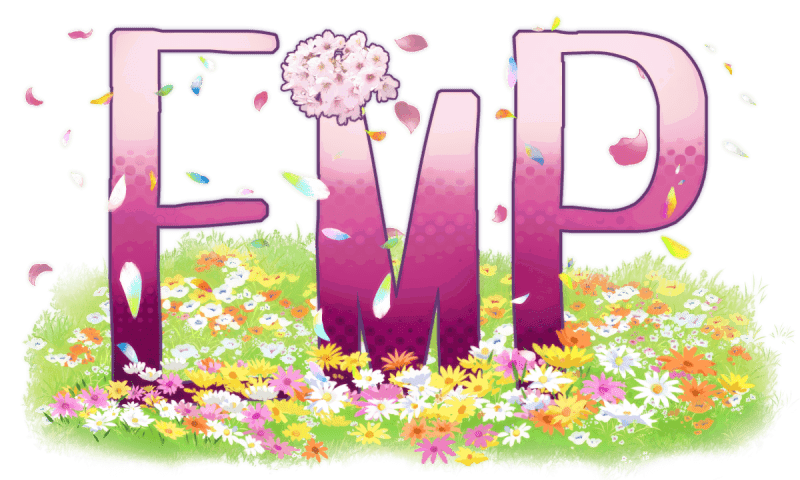そして二人は、先ほどこの近くに落ちてきたであろう“落下物”を探すべく飛行体勢になると、森中を飛び回り始めた。
ようやく見つけた“それ”は木々をなぎ倒し、地面を抉る形で広大な森の中に埋まっていた。周囲は焦臭い臭いに包まれており、その中心には大きなクレーターが刻み込まれている。
その有り様を上空で見ていたガメラは感嘆の声を上げた。
「これは酷いな…隕石でも落ちたのか?」
「だったら宇宙人に注意しないとね」
トトの言うとおり、宇宙人が森の何処かに隠れているかも知れない。それに用心しつつ、二人は余り音を立てない様着地すると、クレーターの中心へと足を進めた。
「UFO…見あたらないね。壊れちゃったのかな?」
「解らん。それにしては人の気配がしないな」
もしかしたら衝撃のショックで……嫌な可能性が頭をよぎる。それにこれだけの痕跡を残しているにも関わらず、UFOの欠片すら見あたらない為、尚更不自然さを感じさせた。やはり隕石だったのだろうか?
そして、恐る恐る歩いてゆく内、抉れたクレーターの中にふと何かが埋まっている事に気づいた。
「お姉ちゃん、これ…!」
「ん?甲羅……?」
何故こんな所に亀の甲羅が?しかもよく見れば、ガメラのそれと似ている。
そして何よりも、それは微かに上下していた。まるで残り少ない生命を補うかの様に。
“これ”を見て、ガメラは一瞬迷ったが、ある決意を下した。
顔すら見ていないが、何としてでも助けなければ。でないと、この甲羅の持ち主は死んでしまう。
「助け出すぞ」
「え!?でも…」
「“これ”からは、敵意が感じられない。寧ろ私と似た感覚がする」
「大丈夫かな?起きたらいきなり襲って…ってお姉ちゃん!」
トトの静止を背中で聞き流しつつ、ガメラはその甲羅のフチを持ち、なるべく揺らさないように土の中からそっと引き抜く。
表面は泥だらけだったものの、そんなに深く埋まっていなかったためか容易く救出できた。
「衰弱はしているが、大きな怪我はないようだな…こんな上空から落ちてきたのに大したものだ」
言いながらうつ伏せだった体を仰向けにすると、ようやく「空からの来訪者」の容姿が明らかになった。
年齢はトトより少し年上くらいのボーイッシュな少女で、少し長めの髪をヘアバンドで留め、若葉色の民族衣装で身を包んでいる。
着物ではなかったものの、風貌と色合いは何もかもガメラと共通していた。
「女の子?」
「らしい。それにしても、一体何処から……」
「う…ん………」
微かな声を上げつつ、少女は目を覚ました。瞳はガメラ族共通なのか澄んだ緑色で、視線をしきりに四方八方へと見回している。
「お、お姉ちゃ…」
「静かに」
不安がるトトを片腕で静止させつつ、ガメラは眼前の少女を凝視しながら問いかける。
「寝起きの所悪いが、1つ質問させてもらう。お前は一体誰だ?」
「…..『ガメラ』」
唐突に告げられた自分と同じ名前。聞き間違いかと思ったが、確かにそう聞こえた。
けれど、今まで自分の同族はトト以外に遭遇した事が無い。だとしたらこの少女はアトランティスの生き残りだろうか?
「お姉ちゃんが2人?何で…」
「私にも…..って、おい!」
2人が戸惑っている間に、『ガメラ』と名乗る少女は意識が遠くなったのか、再び眠りに就いてしまった。
「運ぶぞ。トトも手伝え」
「う、うん」
偶然とはいえギャオス族の襲来から窮地を脱してくれた恩人を背負い、トトは彼女の脚を持つ形になる。
問い質したい事は山のように残るものの、起きた後でたっぷりと訊こうと思いつつ、少女の落下したクレーター地点を跡にした。
少女が目を覚ますと、早速目に入ったのは板張りの天井だった。
直後に体に感じる布団の柔らかさを始め、青畳の匂いと、何かを炊いたような香わしい匂いが嗅覚を刺激し、特に後者に至っては忽ち彼女の食欲を刺激する。
「此処は……」
自分は一体どうしたんだろう。ザノンを討つべく命を捨てる覚悟で宇宙船に飛び込んだと思ったら突然光に包まれて、突如高い高い空の上から落ちた先は見知らぬ森の中だった。
そして防御態勢を解きつつ目を覚ますと、自分は何故か亀を模したかのような人間になっていて、その上普通ではあり得ない緑色の髪をした女性と、茶髪の少女がこちらを凝視していた。
けれど、更にあり得ないのはその身体にある“もの”だった。
自分と同じ人間の姿なのに、甲羅に尻尾が生えていて、その上流暢に言葉を話す。まるで自分とそっくりではないか。
彼女達は姿を変えてはいるものの、ザノンから放たれた新手の刺客だろうか?考えようにも疑問は尽きない。
同時に、ふと自分を僅かな期間ながら育ててくれた少年の顔が脳裏を横切った。今頃彼は何処で、何をしているんだろう。
「……ケイイチ」
誰にも聞こえない様にぽつりと呟いた途端、小さな足音が障子越しから聞こえてきた。
────誰?
先程から嗅覚を刺激してやまない炊き物の匂いをバックに近づいてゆく足音からして、まだ子供にも聞こえる。あちらの方なら恐らく話しやすいだろう。
年長と思わしき緑の髪の女性は、話し方からして自分には取っつきづらそうに感じた。
「…入ります」
考えている内に幼い声が聞こえると、障子がすっと乾いた音を立てて開けられた。
「あ、もう起きたんだ」
入ってきたのはやはり茶髪の少女の方だった。その両手には四角いお盆があり、その上には焼き魚、煮物、白米、白味噌、緑茶の入った湯呑みと、如何にも庶民的な和食料理が鎮座されている。